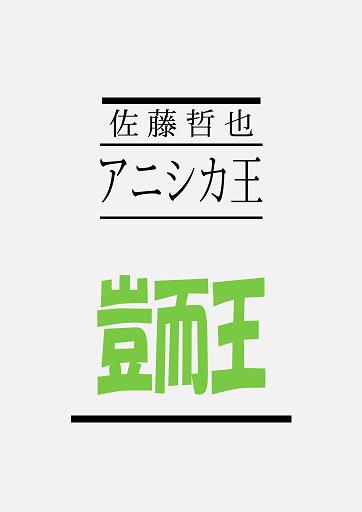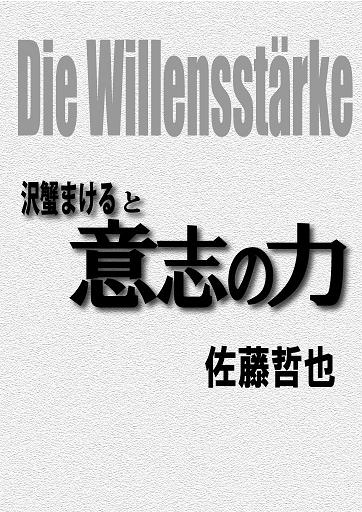|
2011.09.01 thu. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』 を見る。 2011.09.02 fri.
2011.09.03 sat. 午後、ビデオで 『邪神バスターズ』 を見る。ラブクラフトものの、いちおうコメディ。期待していたわけではない。夜、大蟻食と一緒にビデオでセルビア映画 『ランド・オブ・アドベンチャー』 を見る。こちらは拾い物。 2011.09.07 wed. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『ザ・タウン』 を見る。傑作であった。 2011.08.08 thu. 【お知らせ】 『テラシティ』 の誤字・脱字を修正しました。 2011.09.09 fri. ここ最近、DVDで映画を見ようとすると、なんとなく70年代の作品に流れる傾向がある。つまるところ、この時期がわたしの映画鑑賞歴の根っこになっているのであろう。加えて、最近の映画の過剰な設定や無用な饒舌さがいやになっているのではないか、と感じているような気がしないでもない。というわけで今夜は 『刑事マルティン・ベック』と 『テレフォン』 の2本立て。いずれもTSUTAYAの発掘良品。前者はシューヴァル&ヴァール原作のスウェーデン映画で、警察物としては水準だが、クライマックスのヘリコプターの墜落シーンがすばらしい。アラートを鳴らしながら野次馬の頭上に降下してきて、地下鉄の入り口に落ちて横倒しになり、燃え上って、そこへ消防車が出動してきて消火して、というところまできっちりと見せる。後者はドン・シーゲルの後期の作品で、主演はチャールズ・ブロンソン。脚本はピーター・ハイアムズにスターリング・シリファントという豪華版で、アイデアは非常に面白い。 2011.09.10 sat. 蒸し暑い。 2011.09.11 sun. あれから10年。 ジョナサン・リテル『慈しみの女神たち』の「アルマンド」を読み終える。語り手は独ソ戦勃発ののち、ウクライナで反ユダヤ政策の実施を間近に目撃し、神経を病んでクリミアで療養生活を送ったあと、カフカスの戦線に送られる。国防軍およびSSはカフカスでユダヤ人にはまるで見えない山岳ユダヤ人と遭遇し、これはユダヤ人なのか、それともそうではないのかという問題が持ち上がり、状況の安定を優先したい国防軍は山岳ユダヤ人に手を出せば残りの山岳部族が反発すると恐れてユダヤ人ではないと主張し、一方、党組織であるSSは新たな世界観にしたがってユダヤ人であると主張してあくまでも浄化の必要を訴える。両者は決着をつけるためにそれぞれ本国から専門家を呼び寄せ、さらに東方占領地省も専門家を送り込み、すぐ北ではスターリングラードがちょっとやばくなっているし、実はカフカスの戦線もかなり怪しいという状況であるにもかかわらず、じっくりと現地調査をおこなって会議を開き、それぞれの研究成果を発表する。後半に進むにしたがって党官僚と国家官僚の対立の構造がはっきりと現われ、ドイツ東方政策の端っこでも、つまりそういうことがはびこっていたという話が膨大なテキストの隙間に埋まっている。 2011.09.14 wed. ジョナサン・リテル『慈しみの女神たち』の「クーラント」を読み終える。1942年の暮れ、語り手は転属となってカフカスからソ連軍包囲下のスターリングラードへ移動し、そこで初めて実戦の光景を目撃する。そしてドイツ軍の士気、栄養状態などを調べるために各所を訪れ、恐怖と絶望、欠乏と栄養失調を観察する。つまり「あの」スターリングラードで情報収集活動とデスクワークをするのである。しかし語り手も間もなく虱にたかられ、慢性の下痢に悩まされ、虚脱感を味わい、やがて現実感を失って幻想に耽り、耳から膿を垂れ流しながら譫妄状態に陥っていく。崩壊していく第六軍の阿鼻叫喚を残忍なまでに微細に描き、感情との連携がはずれた異様なまでに冷静な筆致は離人症的な効果をもたらして人間性の破壊を描き出す。終盤における感覚の遮断はよくできている。ほぼ全編にわたって悪臭が漂い、死体の山が登場し、なにしろスターリングラードなので救いはない。 2011.09.15 thu. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『戦火のナージャ』 を見る。 2011.09.16 fri. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『ヨギ&ブーブー わんぱく大作戦』 を見る。いや、つまり『クマゴロー』の実写映画化。 2011.09.17 sat. 『世界侵略:ロサンゼルス決戦』 を見る。 2011.09.18 sun. 蒸し暑い。ぐったりしている。 2011.09.19 mon. 引き続きぐったりしている。 2011.09.20 tue. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『ザ・ライト』 を見る。 2011.09.21 wed. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『ベスト・キッド』 を見る。 2011.09.23 fri. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『アレクサンドリア』 を見る。 2011.09.24 sat. 気持ちのいい天気なので大蟻食と一緒に散歩をする。買い物をして帰宅。 2011.09.25 sun. 気温がさがってきたせいか、鼻の調子がよろしくない。 2011.09.28 wed. 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『X-MEN: ファースト・ジェネレーション』 を見る。 2011.09.29 thu. ジョナサン・リテル『慈しみの女神たち』を読み終える。実を言うと読み進めていくあいだ、もしかしたら調べたことを全部書いているのではあるまいか、文章を飾りすぎているのではあるまいか、といったことを考えていたが、最後まで読みとおしてみると構成上の必然性が浮かび上がる。無駄に思えた部分は語り手の拡張された感受性に連絡し、語り手はその感受性においてカフカスの風光明媚な山を一望し、路傍に咲く花に気づき、飛び立つ鳥のしぐさを見つめ、公園に転がる女の死体を記憶にとどめ、ドイツ東方政策における党官僚と国家官僚の対立を眺め、スターリングラードの臭気に顔をしかめ、アウシュヴィッツにおける数々の不正と不手際を目撃し、ベルリン攻防戦の悲惨を観察する。反応はほぼいつも同じ地平に展開し、頭を撃ち抜かれて朦朧としながら幻影を中をさまよっても、心象の連続は保たれることになるのである。そしてこのとめどのない連続性と、その連続性をよいことに不断に押し寄せてくる戦争の表象が悪臭芬々たる死体の山や人間の残骸となって語り手を侵し、語り手はこれに対抗するために、ほとんど幼児的なまでの執拗さで過去に執着することになる。しかし語り手が取り出す過去は同じ過去を共有する姉の言葉と態度によって損なわれ、語り手はこの損傷を修復するために記憶の外側にある過去を覗き、そこに背を向けると幻想の中に姉を描くことで架空の現在を作り出す。この異常な行動の起点にあるのは語り手自身がその立場から自動的に関わった悪であり、そこに続くのは言わば業務化された悪から逃避することへの迂遠な渇望であり、現実を希釈しようと試みる奇怪な防御反応である。背景が背景だけに悪は語り手の背後を覆い尽くし、したがって語り手がオレステスであるとすれば、その犯罪は語り手の家庭にとどまるものではなく、同時にエリニュスもまた語り手を追う二人の刑事に還元されるだけではなく、語り手を囲む環境全体に及んでいく。戦争とは復讐の女神だからである。長い、と言えばやはり長いような気がしないでもないし、語り手の経歴が都合よくあちらこちらにぶつかりすぎているような気もするが、綿密に調査され、よく構想された大作であり、各所で提示される状況を単に眺めていくだけでも面白いし、ヒムラー、アイヒマン、ヘスといった「著名人」の造形も興味深い。なお、スターリングラード攻防戦についてはアントニー・ビーヴァー『スターリングラード 運命の攻囲戦 1942-1943』を、ベルリン攻防戦については同じくビーヴァーの『ベルリン陥落1945』を、「特別行動」と当事者の心理状態についてはクリストファー・ブラウニング『普通の人びと ホロコーストと第101警察予備大隊』およびダニエル・J・ゴールドハーゲン『普通のドイツ人とホロコースト』をお勧めする。 夜、大蟻食と一緒にビデオで 『酔いがさめたら、うちに帰ろう。』 を見る。 |
< 亭主の日々 >